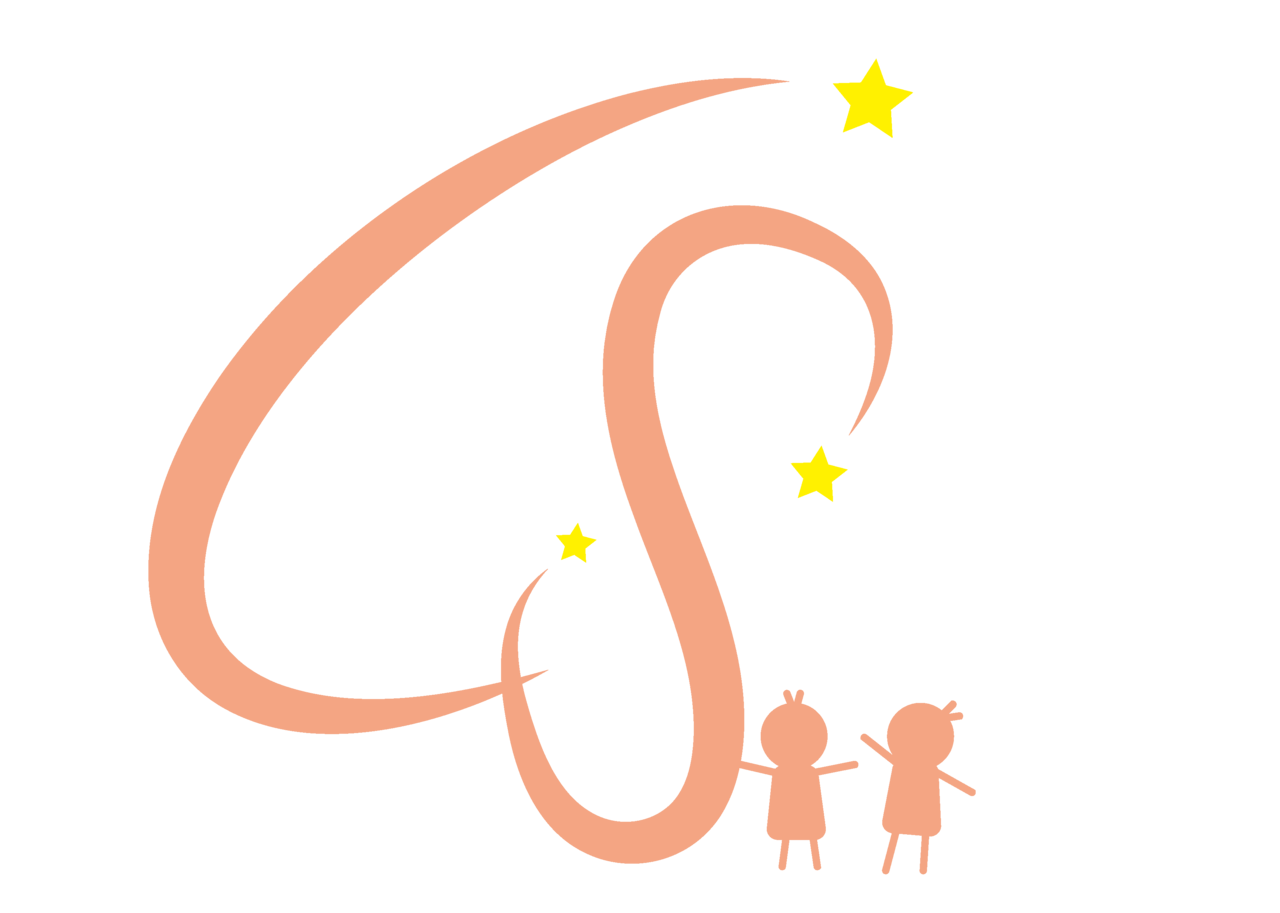あの頃は若かった中村です。こんにちは。
今回のブログではお役立ち情報として、私が過去に無理解だったためにイライラしたことを脳の機能(wisc5)と関連付けて紹介します。わが子に勉強を教える親御さん、学校や塾で生徒に授業をする先生にとって、脳の機能にどのようなものがあるのか、学習指導をする時にどのように関係するのかを知っているのは大切です。

失敗例その1は、問題を解いたりノートを取ったりするのが遅い生徒が居てイライラしたことでした。脳の機能の「処理速度」のことを知らなかった私は、生徒に「急いでやって。」「次の説明が必要だから早くノート写しとって。」と言ったことがあります。私がイライラしていたのも伝わったことでしょう。ごめんなさい!
ここまで読んで、中村ってそんなこと言ってたんだ、わかってないね、と思った方はこの後の記事を読み飛ばしていただいて構いません。今の私なら、脳の機能の「処理速度」について知っていますので、イライラして「急いでよ!」とか「早くやりなよ。」なんて言ったりはしません。なぜなら人によってはこの「処理速度」がゆっくりなので、たとえ本人が頑張って計算問題を急いで解いていても、早く授業の板書をノートに書き写そうと努力していても早くすることは無理だからです。
(wisc5の項目の1つ)処理速度とは
処理速度とは脳の機能の1つで、視覚的な情報を素早く正確に処理して行動する能力に関わるものです。処理速度が速い人は次々に問題を解き進めることが出来るので、テストを時間内に終わらせることが出来ます。遅い人は板書を書き写すのに時間がかかったり、道具を使った作業に時間がかかったりします。ちなみにwisc5とは脳の機能を見る検査の1つで、処理速度の他にも言語理解、視空間、流動性推理、ワーキングメモリーについて見ることが出来ます。
今ではわかります。「x+3=4x-6」の方程式を解くのに移項計算を素早くして「-3x=-9」→両辺を-3で割って「x=3」と数秒で答えを出す生徒がいることを。考えながら計算して、場合によっては途中式を書いて符号や数字の処理をして1分以上かけて答えを出す生徒がいることを。
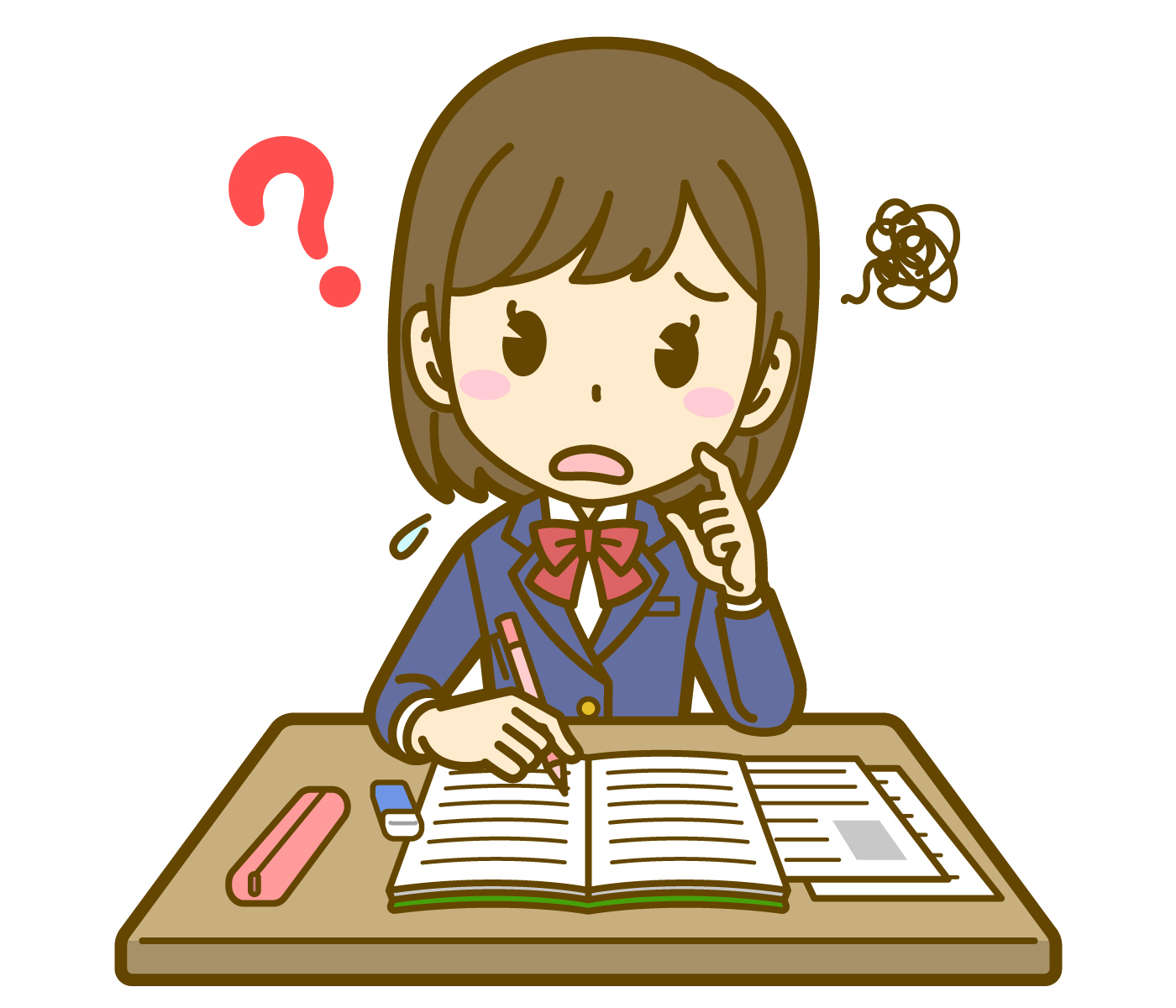
数秒で計算できる親御さんや処理速度のことをわかっていない先生が、処理速度がゆっくりな生徒に対してイライラして、思わず「何やってんの、急いでやりなよ!」と言ってしまう場合があることも。
20代だった私は処理速度が人によって違うことを知りませんでしたので、かつて勤めていた大手の学習塾で、ノートを書き写すのが遅い生徒に早くするよう言っていたのでした。大手の学習塾ですから授業のやり方についての研修がありましたが、脳の機能の「処理速度」については教えてくれませんでした。そんな私は生徒を傷つけることを普通にやっていて、そのことに全く気付いていないのでした。

今なら書ける範囲で書き写せば良い、写真にとっておいて後でノートに写してもよい、と対応します。「とりあえず次の内容に移るから板書消させてもらうね。ごめんね。」と声をかけます。いや、言うのは「ごめんね。」ではなく「だいぶ写せたね、ナイスだ。」ですね!
こんな失敗談でした。いかがでしたか?ではまた!